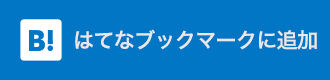将来、可愛いハリネズミが飼育できなくなる…かもしれません。
なぜ飼育できなくなるのか、何に気を付けるべきか考えてみましょう。
他人事だと考えずに一度考えてみてください。たった1人の飼い主の身勝手によって日本中のペットショップからハリネズミが消えるかもしれません。
特に公園などの屋外でハリネズミを遊ばせる事がある飼い主の方にはぜひ目を通して欲しいと思います。
スポンサーリンク
この記事の目次
外来生物法とは

最初に少しだけ専門的な話をさせてください。
もともとはその地域にいなかった、人間の手によって他の地域から入ってきた生物を外来生物*と呼びます。
*外来種・移入種・帰化種・侵入種とも呼ばれます。
この外来生物によって日本にもとからいた生物(在来種)が駆逐されたり、交雑(別の種とのかけあわせ、雑種)による遺伝子汚染、農作物への被害、人への危害の恐れや、生態系を守る目的で2005年に制定された法律が外来生物法*です。
*正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
この外来生物法によって指定されるのが次項で説明する「特定外来生物」です。
特定外来生物とは

外来生物法によって指定された動植物である「特定外来生物」は、許可がなければ飼育・輸入・栽培することができません。
また、野外に放つ・植える・他人に譲渡・販売することも禁止されています。
さらに許可を受けて飼育する場合であっても原則「個体識別措置」が義務付けられるなど厳重な管理を行う必要があります。
特定外来生物の例

特定外来生物として広く知られているのはブラックバスです。
北米原産の淡水魚のブラックバスは魚食性が強く、日本に移入されたことにより在来種が減ったとする学術論文もあります。
このほかにもブルーギル・アライグマ・オポッサム・イタチ・マングース・カミツキガメ・アメリカザリガニなどの生物が特定外来生物に指定されています。
そして特定外来生物の中には「ハリネズミ」も含まれているのです。
ハリネズミは飼ってはいけないの?

「特定外来生物にハリネズミが指定されている」と前項でお話ししましたが、ペットショップで販売されているハリネズミは飼育できます。
正確に言うと、ヨツユビハリネズミ(ピグミーヘッジホッグ)は飼育することができます。
ハリネズミは大きく5種類に分けられており、特定外来生物に指定されているのはハリネズミ属(Erinaceus(エリナケウス))です。
ヨツユビハリネズミは「アフリカハリネズミ属(Atelerix)」に属しているため、現時点では特定外来生物には指定されていません。
詳しくは⇒【ハリモグラ】ハリネズミはネズミじゃない!?徹底解説
なぜハリネズミが特定外来生物に指定されているの?

マンシュウハリネズミ(アムールハリネズミ)が静岡県や神奈川県などで野生化し鳥の雛や卵、昆虫を捕食し生態系に影響を与えた例が実際にありました。
そしてその結果、マンシュウハリネズミをはじめとして、ヒトイロハリネズミ、ナミハリネズミが特定外来生物に指定されました。
環境省は「ヨーロッパ・アジア原産のハリネズミは、日本の冬にも対応が可能であり、アフリカ産種であっても亜熱帯地域などでは十分に定着できる可能性がある」と説明しています。
ヨツユビハリネズミが飼育できなくなる?

ヨツユビハリネズミ(ピグミーヘッジホッグ)は現時点では特定外来生物に指定されていません。
しかし環境省は「アフリカ産種であっても亜熱帯地域などでは十分に定着できる可能性がある」としています。
つまりアフリカ産種のヨツユビハリネズミが亜熱帯地域などで定着(野生化)し生態系に影響を及ぼすことがあれば特定外来生物に指定される可能性は十分にありうるということです。
ヨツユビハリネズミが特定外来生物にならないために

マンシュウハリネズミが特定外来生物に指定されるに至った経緯は次の通りです。
- 何者かがハリネズミを逃がす(または遺棄)
- ハリネズミが定着(野生化・繁殖)し生態系に影響
- ハリネズミが特定外来生物に指定
ヨツユビハリネズミも決して例外ではないことがここまでの話でお分かりいただけたと思います。
飼い主一人ひとりが責任を持って飼育することがとても大切です。
その責任を負わずハリネズミを遺棄してしまうと「日本中のハリネズミが飼育できなくなる」ということになりかねません。
まとめ

ハリネズミを飼うということは同時に責任を負う事でもあるということを十分理解してください。
SNS上では複数のハリネズミを公園などに連れていき、一斉に野放しにした結果行方不明になってしまったという不届き千万な話を聞いたことがあります。
ハリネズミの安全上はもちろんのこと、今回の外来生物法の観点でも絶対にあってはならない事案です。
飼い主全員で日本のヨツユビハリネズミを飼育できる環境を守っていきましょう。
スポンサーリンク